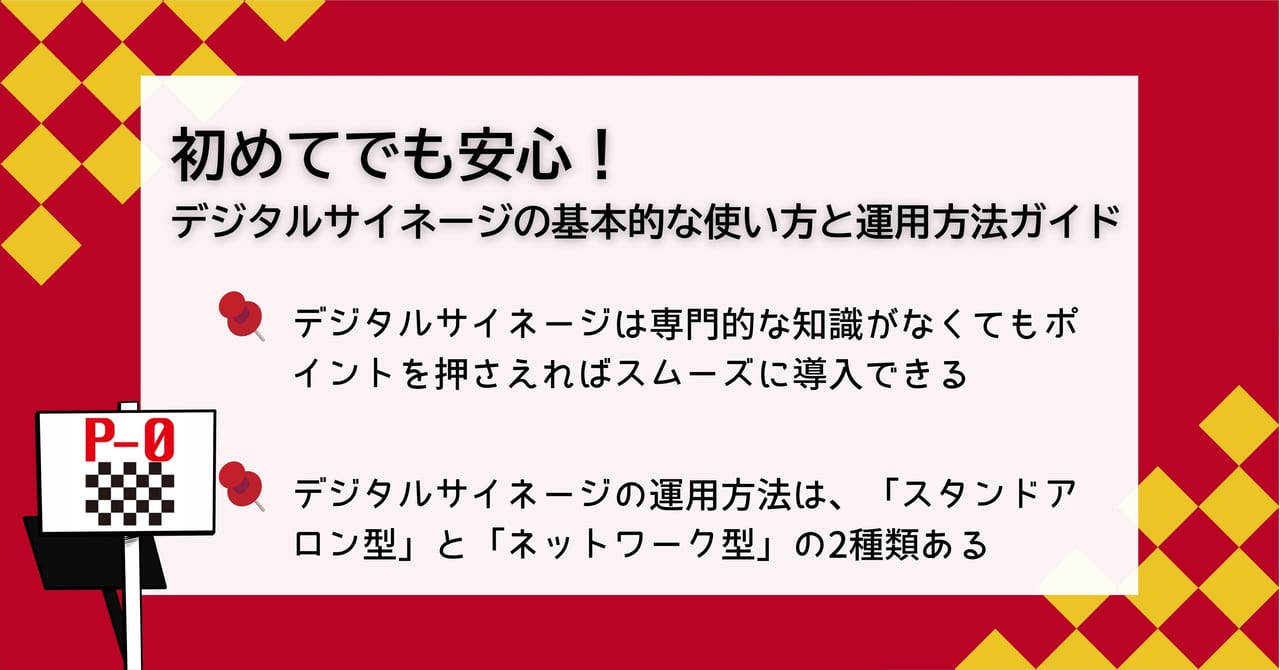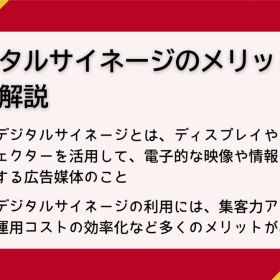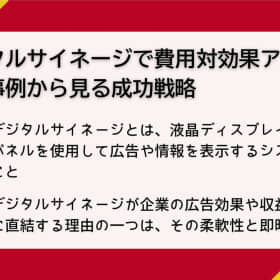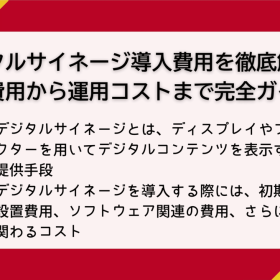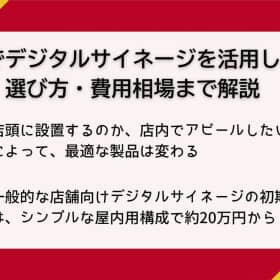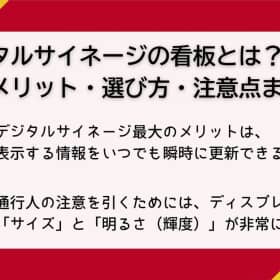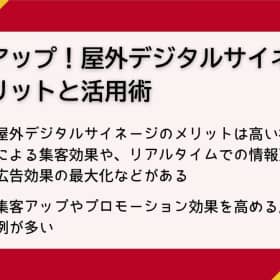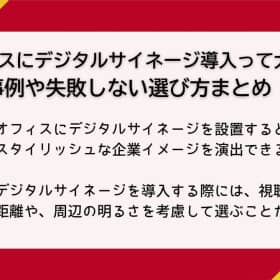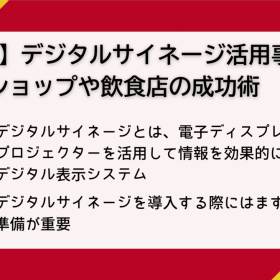デジタルサイネージ
初めてでも安心!デジタルサイネージの基本的な使い方と運用方法ガイド
デジタルサイネージという言葉を耳にしたものの、「どこから始めたらいいのか分からない…」という方も多いのではないでしょうか。実は、仕組みと使い方のポイントさえ押さえれば、専門知識がなくても運用を始められます。
本記事では、初めての方でも安心して導入できるように、必要な機材やコンテンツの作成方法、配信の仕組みまでを3ステップでわかりやすく解説しています。USBメモリを使ったシンプルな方法から、ネットワーク経由の効率的な運用まで幅広くご紹介していますので、ご自身の目的に合った活用方法が見つかるヒントになれば幸いです。
目次
デジタルサイネージとは?基本的な仕組みをわかりやすく解説!
デジタルサイネージとは、ディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発信するシステムの総称です。「電子看板」や「デジタル看板」とも呼ばれ、駅や商業施設、店舗、オフィスなど、さまざまな場所で活用されています。従来のポスターや看板とは異なり、動画や音声を含む多様なコンテンツを表示できるほか、遠隔操作で表示内容をリアルタイムに更新できるのが大きな特長です。
本章では、デジタルサイネージを導入する上で知っておきたい基本的な仕組みについて解説します。
デジタルサイネージを構成する3つの要素
デジタルサイネージは、単にディスプレイを設置するだけでは機能しません。主に「ディスプレイ」「再生機」「コンテンツ管理システム(CMS)」という3つの要素が連携することで、情報を発信する仕組みが成り立っています。
ディスプレイ(モニター)
コンテンツを映像として表示するための画面です。一般的には液晶ディスプレイが主流ですが、屋外の大型ビジョンなどではLEDディスプレイが使われることもあります。設置場所に応じて、屋内の明るさに適した「屋内用」と、太陽光の下でも視認性が高く、防水・防塵性能を備えた「屋外用」から選択します。
再生機(STBや内蔵プレーヤー)
静止画や動画などのコンテンツデータを再生するための機器です。一般的にはSTB(セットトップボックス)と呼ばれる専用の小型PCをディスプレイに接続して使用します。近年では、ディスプレイ本体に再生機能が組み込まれた「プレーヤー内蔵型」も増えており、配線をシンプルにできるメリットがあります。
コンテンツ管理システム(CMS)
表示するコンテンツの登録や、配信スケジュールの設定、複数ディスプレイの一括管理などを行うためのソフトウェアです。Content Management Systemの略称で、特に後述するネットワーク型のデジタルサイネージを運用する上で中核となるシステムです。Webブラウザから操作できるクラウド型のCMSが主流で、遠隔地からでも簡単に表示内容を更新できます。
スタンドアロン型とネットワーク型の違い
デジタルサイネージの運用方法は、コンテンツの更新方法によって「スタンドアロン型」と「ネットワーク型」の2種類に大別されます。それぞれの特徴やメリット・デメリットが異なるため、目的や設置台数に応じて最適なタイプを選ぶことが重要です。
| 項目 | スタンドアロン型 | ネットワーク型 |
| コンテンツ更新方法 | USBメモリやSDカードに保存したデータを、ディスプレイに直接接続して更新します。 | インターネット回線を通じて、CMSから遠隔でコンテンツを更新・配信します。 |
| 主な利用シーン | 店舗の入り口やレジ横など、1台のみを単独で運用する場合に適しています。 | 複数店舗や多拠点に設置したディスプレイを一括で管理・運用する場合に適しています。 |
| コスト | ネットワーク環境が不要なため、初期費用を抑えやすい傾向にあります。 | STBやCMSの利用料(月額・年額)が発生するため、スタンドアロン型より高価になる場合があります。 |
| 運用管理 | 手軽に始められますが、コンテンツ更新のたびに現地での作業が必要です。 | リアルタイムな情報更新やスケジュール配信が可能で、効率的な運用ができます。 |
デジタルサイネージの基本的な使い方!導入から配信までの3ステップ
デジタルサイネージの導入は、専門的な知識がなくてもポイントを押さえればスムーズに進められます。ここでは、機材の準備からコンテンツの配信まで、大きく3つのステップに分けて基本的な使い方を解説します。
STEP1 必要な機材の準備と設置
最初に、デジタルサイネージを運用するために必要な機材を揃え、適切な場所に設置します。設置場所を選ぶ際は、ターゲットとなる人々の視線に入りやすいか、通行の妨げにならないか、そして電源が確保できるかを確認することが重要です。運用方法によって必要な機材が異なるため、スタンドアロン型とネットワーク型の違いを理解しておきましょう。
スタンドアロン型とネットワーク型の機材準備
スタンドアロン型は単体で運用するシンプルな構成、ネットワーク型は遠隔操作が可能な構成です。それぞれのタイプで必要となる主な機材を以下にまとめました。
| タイプ | 必要な機材 | 特徴 |
| スタンドアロン型 |
|
インターネット接続が不要で、比較的安価に導入可能。コンテンツの更新は、USBメモリなどを直接ディスプレイに接続して手動で行う。 |
| ネットワーク型 |
|
インターネットを介して、遠隔地にあるPCからコンテンツの更新や配信スケジュールの設定が可能。複数拠点への一斉配信にも対応できる。 |
STEP2 表示するコンテンツの作り方
デジタルサイネージの効果は、表示するコンテンツの質に大きく左右されます。魅力的でわかりやすいコンテンツを準備しましょう。必ずしも専門的な動画編集ソフトやデザインツールが必要なわけではなく、身近なアプリケーションでも作成可能です。
PowerPointを使った簡単な静止画コンテンツ作成
多くのオフィスで導入されているMicrosoft PowerPointは、手軽に静止画コンテンツを作成できる便利なツールです。以下の手順で作成できます。
- スライドサイズの変更: PowerPointを開き、「デザイン」タブから「スライドのサイズ」→「ユーザー設定のスライドのサイズ」を選択します。ディスプレイの解像度に合わせてサイズを指定します(例: フルHDの場合は幅50.8cm、高さ28.58cm、または1920px × 1080px)。
- デザインの作成: テキストボックスや図形、画像を配置して、伝えたい情報をデザインします。視認性を意識し、文字は大きく、配色はシンプルにまとめるのがポイントです。
- 画像の書き出し: コンテンツが完成したら、「ファイル」→「エクスポート」→「ファイルの種類の変更」から「JPEG」または「PNG」形式を選んで保存します。
動画コンテンツ作成の基本
動きのある動画は、静止画よりも人々の注意を引きつけやすいというメリットがあります。Windowsに標準搭載されている「フォト」アプリのビデオエディター機能や、Canvaのような無料のオンラインツールを使えば、専門知識がなくても簡単な動画を作成できます。作成する際は、音声なしでも内容が伝わるようにテロップを入れたり、15秒~30秒程度の短い時間で情報をまとめたりすることが重要です。スマートフォンのカメラで撮影した映像も手軽な素材として活用できます。
効果的なコンテンツ作りのコツ
より多くの人に関心を持ってもらうためには、コンテンツ作りにいくつかのコツがあります。以下の点を意識するだけで、コンテンツの訴求力は格段に向上します。
- ターゲットを明確にする: 「誰に」「何を」伝えたいのかを具体的に設定することで、メッセージがぶれなくなります。
- 情報はシンプルに: 通行人が一瞬で内容を理解できるよう、テキストや要素を詰め込みすぎず、最も伝えたい情報に絞り込みましょう。
- – 視認性の高いデザイン: 背景と文字のコントラストをはっきりさせ、遠くからでも読めるフォントサイズを心がけます。行動を促す一言を入れる: 「詳しくはWEBで検索」「2階特設コーナーへ」といった具体的な行動を促す言葉(CTA)を入れると、次のアクションにつながりやすくなります。
STEP3 コンテンツの登録と配信設定
コンテンツが完成したら、いよいよディスプレイに表示させるための最終ステップです。この登録・配信方法は、スタンドアロン型とネットワーク型で大きく異なります。
USBメモリを使ったスタンドアロン型の使い方
スタンドアロン型は、USBメモリを使って手軽にコンテンツを更新するのが一般的です。非常にシンプルな手順で配信できます。
- 作成した静止画(JPEG/PNG)や動画(MP4など)のファイルをUSBメモリに保存します。
- デジタルサイネージ用ディスプレイの指定のUSBポートに、そのUSBメモリを挿入します。
- 多くの場合、自動でコンテンツの再生が始まります。リモコンや本体のメニュー画面から、再生したいファイルを選択したり、リピート再生やスライドショーの間隔を設定したりすることも可能です。
この方法は手軽ですが、コンテンツを更新するたびに現地でUSBメモリを抜き差しする手間がかかります。
CMSを使ったネットワーク型の使い方
ネットワーク型は、CMS(コンテンツ管理システム)を利用して、遠隔からコンテンツの登録や配信スケジュールを管理します。複数台のディスプレイも一元管理できるのが大きな強みです。
- オフィスのPCなどから、Webブラウザを使って指定されたURLにアクセスし、IDとパスワードでCMSにログインします。
- 管理画面上で、作成したコンテンツファイルをアップロードします。
- どのディスプレイに、どのコンテンツを、いつからいつまで表示させるか、といった配信スケジュールを作成・設定します。曜日や時間帯ごとに表示内容を変えるといった詳細な設定も可能です。
- 設定を保存すると、インターネット経由で各ディスプレイに配信情報が送られ、スケジュール通りにコンテンツが自動で再生されます。
CMSを利用することで、リアルタイムな情報更新や計画的な運用が効率的に行えます。
【目的別】デジタルサイネージの効果的な使い方と活用事例
デジタルサイネージは、ただ映像を流すだけの装置ではありません。ここでは最大限の効果を引き出すために、代表的な3つのシーン「店舗」「オフィス」「施設・イベント」に分け、具体的な使い方と活用事例を解説します。
店舗での使い方(販促・メニュー訴求)
店舗におけるデジタルサイネージの主な目的は、集客力の向上と売上アップです。通行人の注目を集め、入店を促し、店内での購買意欲を高めるためのツールとして非常に有効です。時間帯や天候に合わせて表示内容を切り替えることで、より効果的なアピールが可能になります。
例えば、飲食店ではランチタイムにはお得なセットメニューを、ディナータイムにはアルコール類やコース料理を訴求するなど、ターゲットに合わせた情報発信ができます。アパレル店では、モデルが商品を着用している動画を流すことで、顧客は着用イメージを具体的に掴むことができ、購入へと繋がりやすくなります。
| 業種 | 効果的な使い方・コンテンツ例 | 期待できる効果 |
| 飲食店・カフェ | ・店頭でシズル感のある料理動画を放映
・ランチ、ディナーでメニューを自動切替 ・雨の日限定クーポンなどを表示 |
・入店率の向上
・客単価アップ ・リピーター促進 |
| 小売店・アパレル | ・タイムセールやキャンペーン情報の告知
・モデルによる着用動画やコーディネート提案 ・レジ横でのおすすめ商品(ついで買い)訴求 |
・衝動買いの誘発
・ブランドイメージ向上 ・顧客体験の向上 |
| スーパーマーケット | ・特売情報や旬の食材をアピール
・食材を使ったレシピ動画の放映 ・生産者の顔が見えるコンテンツ |
・特定商品の販売促進
・関連商品の合わせ買い促進 ・食の安全性・信頼性アピール |
オフィスでの使い方(情報共有・ブランディング)
オフィスでのデジタルサイネージ活用は、社内に向けては「情報共有の円滑化」、社外に向けては「企業ブランディング」という2つの大きな目的があります。従業員が必要な情報をタイムリーに得られる環境は、業務効率やエンゲージメントの向上に繋がります。
エントランスや受付に設置すれば、来訪者に対して事業内容や製品・サービスの紹介、企業理念などを効果的に伝えることができます。洗練された映像は、企業の先進性をアピールするのにも役立ちます。また、社員食堂や休憩スペースでは、連絡事項や健康経営に関する情報などを配信し、社内コミュニケーションを活性化させる使い方が考えられます。
| 設置場所 | 効果的な使い方・コンテンツ例 | 期待できる効果 |
| エントランス・受付 | ・来訪者へのウェルカムメッセージ
・企業理念や事業内容の紹介動画 ・自社製品やサービスのプロモーション |
・企業ブランディング強化
・来訪者の待ち時間短縮・満足度向上 ・先進的な企業イメージの構築 |
| 執務エリア・共有スペース | ・全社的なお知らせや売上速報
・社内イベントの告知やレポート ・新入社員の紹介、理念の浸透 |
・社内コミュニケーションの活性化
・情報伝達の迅速化・効率化 ・従業員エンゲージメントの向上 |
施設やイベントでの使い方(案内・誘導)
駅や空港、商業施設、病院といった不特定多数の人が利用する施設や、大規模なイベント会場では、デジタルサイネージは「案内・誘導」の役割を担います。紙のポスターとは異なり、リアルタイムで情報を更新できるため、緊急時のお知らせにも迅速に対応できます。
例えば、商業施設ではフロアマップやイベント情報を、空港ではフライト情報やゲート案内を多言語で表示することで、利用者の利便性を大きく向上させます。タッチパネル式のサイネージを導入すれば、利用者が自ら情報を検索できるインタラクティブな案内も可能です。これにより、インフォメーションカウンターの混雑緩和にも繋がります。
| 施設・場所 | 効果的な使い方・コンテンツ例 | 期待できる効果 |
| 交通機関(駅・空港) | ・運行情報、遅延・運休案内
・乗り換え案内、時刻表 ・多言語での案内表示 |
・利用者の利便性向上
・スムーズな誘導による混雑緩和 ・緊急時の迅速な情報提供 |
| 商業施設・ホテル | ・フロアマップ、テナント案内
・イベントやセールの告知 ・レストランの空席情報 |
・回遊性の向上
・施設全体の売上アップ ・顧客満足度の向上 |
| 病院・クリニック | ・診療の待ち時間や順番の表示
・休診や担当医変更のお知らせ ・健康に関する啓発情報 |
・患者の待ち時間ストレス軽減
・院内業務の効率化 ・スムーズな院内案内 |
Q&A|デジタルサイネージの使い方でよくある質問
デジタルサイネージの導入や運用を検討する中で、多くの方が抱える疑問にお答えします。
コンテンツの更新頻度はどのくらいが適切?
コンテンツの最適な更新頻度は、デジタルサイネージを設置する目的や場所によって大きく異なります。一概に「この頻度がベスト」とは言えませんが、一般的な目安は以下の通りです。
例えば、飲食店のランチメニューのように情報の鮮度が重要な場合は毎日更新するのが効果的です。一方で、オフィスの理念や行動指針といった普遍的な情報を表示する場合は、頻繁な更新は必要ありません。大切なのは、「誰に、何を伝えたいか」を常に意識し、情報が古くならないように運用計画を立てることです。定期的に内容を見直すだけでも、通行人の関心を引きつけ、サイネージの効果を持続させることができます。
屋外で使う場合の注意点はある?
屋外でデジタルサイネージを使用する場合、屋内用とは異なる特別な配慮が必要です。屋外環境は天候や気温の変化が激しく、太陽光の影響も受けるため、専用の設計が施された機器を選ばなければなりません。主な注意点は以下の通りです。
| 項目 | 屋外で求められる仕様・注意点 | 解説 |
| 防水・防塵性能 | IP規格(IP55など)に対応したモデルを選ぶ | 雨や砂埃、塵などから内部の電子機器を保護するために必須の性能です。 |
| 輝度(明るさ) | 1,500cd/m²以上の高輝度ディスプレイを推奨 | 日中の強い太陽光の下でも映像がはっきりと見えるように、屋内用(約350〜700cd/m²)よりも格段に明るいディスプレイが必要です。 |
| 熱対策 | 冷却ファンや空調機能を内蔵しているか確認 | 直射日光による温度上昇や、機器自体の発熱を適切に排出し、故障や性能低下を防ぎます。 |
| 耐久性・安全性 | 堅牢な筐体や強化ガラス、盗難防止対策が施されているか | 衝撃やいたずら、強風などから機器を守るための耐久性が求められます。設置場所によっては屋外広告物条例などの法令確認も必要です。 |
これらの条件を満たした屋外専用のデジタルサイネージを選ぶことで、天候に左右されず、安全かつ安定した運用が可能になります。
故障かなと思ったら確認することは?
「画面が映らない」「コンテンツが再生されない」といったトラブルが発生した場合、専門の業者に連絡する前に、ご自身で確認できる基本的な項目があります。以下のチェックリストを試してみてください。
| チェック項目 | 確認内容 |
| 電源の確認 |
|
| 接続の確認 |
|
| 再生機の確認 |
|
| 入力切替の確認 |
|
これらの基本的な項目を確認しても症状が改善しない場合は、機器の故障である可能性が考えられます。無理に操作を続けず、購入した販売代理店やメーカーのサポートセンターに、製品の型番や具体的な症状を伝えて相談してください。
まとめ
ここまで、デジタルサイネージの基本的な仕組みから、導入に必要な機材、コンテンツの作成・配信方法までをご紹介してきました。「難しそう」と感じていた方も、実は身近なツールで始められることや、自社に合わせた柔軟な運用が可能であることがご理解いただけたのではないでしょうか。販促や情報共有、案内表示など、さまざまな場面で活用できるデジタルサイネージ。ぜひ本記事を参考に、効果的な情報発信を始めてみてください。
デジタルサイネージの導入をご検討中の方や、デザイン・設置についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問合せください。
あなたの理想に合ったご提案や製作を、専門スタッフが丁寧にサポートします。
![看板製作、ポスター印刷ならP-0 Grand Prix [ピーゼログランプリ]](https://p0gp.com/wp-content/uploads/2020/06/logo-sp-c.png)