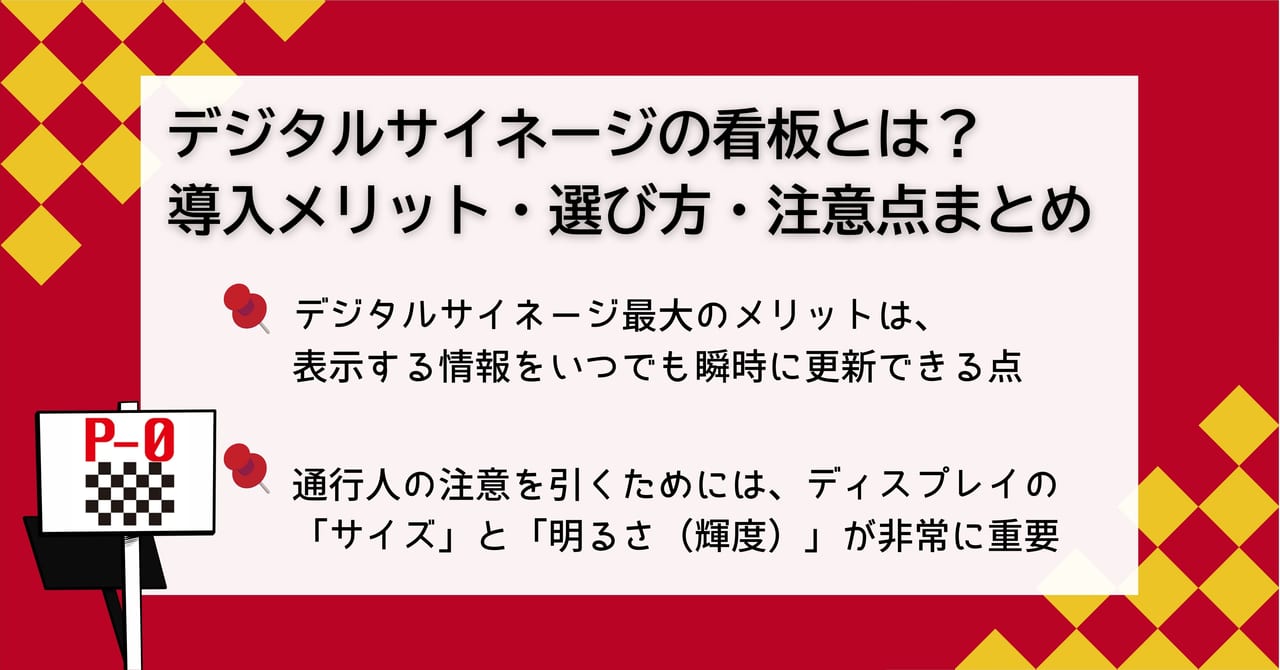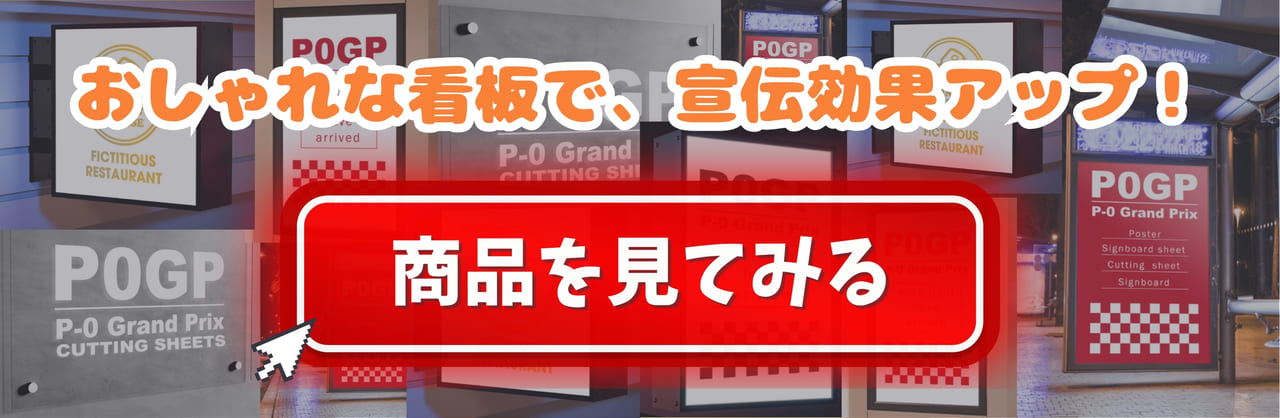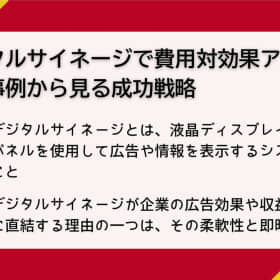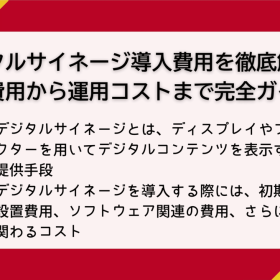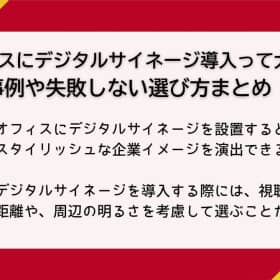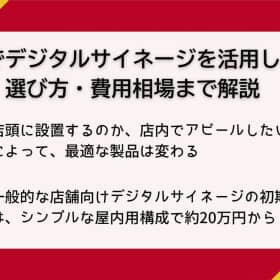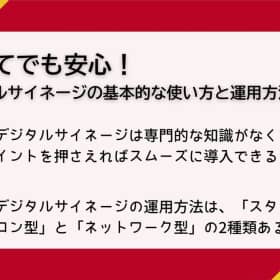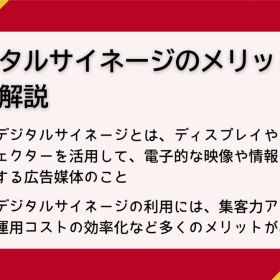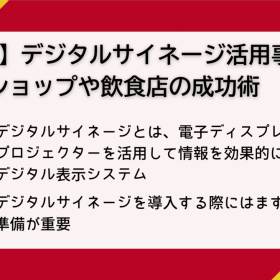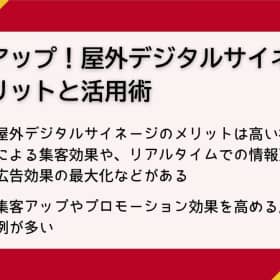デジタルサイネージ
デジタルサイネージの看板とは?導入メリット・選び方・注意点まとめ
デジタルサイネージ看板とはどのようなものかご存じでしょうか?
従来の看板と違い、映像や音声を活用してリアルタイムで情報を発信できるため、近年さまざまな業種で導入が進んでいる従来の静的な広告とは一線を画す存在です。
本記事では、デジタルサイネージ看板の基本から、導入時のメリット・デメリット、費用を抑える方法、失敗しない選び方、さらには業種別の活用事例や設置時の注意点まで、実務目線でわかりやすく解説いたします。ぜひ、導入をご検討中の方は最後までご覧ください。
目次
デジタルサイネージ看板の基本をわかりやすく解説!
ここでは、デジタルサイネージの基本的な知識と、私たちがよく目にする従来の看板との違いについて、分かりやすく解説します。
そもそもデジタルサイネージとは?従来の看板との違いを解説
デジタルサイネージとは、ディスプレイやプロジェクターなどの電子機器を使用して、映像や画像、文字情報などのコンテンツを表示する広告・情報発信メディアを指します。駅や商業施設、店舗の店頭などで見かけることが多く、近年では企業の受付やオフィス内など、さまざまな場面で導入が進んでいます。
従来の看板との大きな違いは、「表示内容を自由に変えられる点」です。紙やパネルによるアナログ看板の場合、内容を変更する際には張り替えや再印刷が必要でしたが、デジタルサイネージであれば、パソコンやクラウド経由で即座に情報の差し替えが可能です。そのため、時間帯や曜日ごとに表示内容を変えるなど、柔軟で戦略的な運用が実現できます。
また、動画やアニメーションなどの動的なコンテンツを表示できる点も大きな特長です。視認性や印象に残る表現が求められる現代において、デジタルサイネージは従来の看板に代わる新たな選択肢として注目されています。
デジタルサイネージを看板として導入する3つのメリット
ここでは、デジタルサイネージの特に重要な3つのメリットをピックアップし、その魅力と効果を具体的に解説します。
情報をリアルタイムで更新でき訴求力が高い
デジタルサイネージ最大のメリットは、表示する情報をいつでも瞬時に更新できる点です。従来のポスターや看板は、一度設置すると内容の変更には印刷や貼り替えの手間とコストが発生しました。しかし、デジタルサイネージなら、パソコンやスマートフォンから遠隔操作でコンテンツを更新できます。
これにより、「本日のランチメニュー」や「タイムセール情報」、「緊急のお知らせ」など、鮮度が重要な情報をタイムリーに発信することが可能です。顧客のニーズや状況に合わせて最適な情報を届けることで、高い訴求効果が期待できます。
動画や音声を活用し通行人の視線を集める
静止画が基本の従来の看板に対し、デジタルサイネージは動画や音声を活用できるのが大きな強みです。動きのある映像は、静止画に比べて人の注意を引く効果が格段に高いとされています。通行量の多い場所でも、動きと音で視線を惹きつけ、店舗や商品への関心を高めることができます。
例えば、飲食店の店先で調理シーンのシズル感あふれる動画を流したり、アパレルショップでモデルが服を着て動いている映像を見せたりすることで、写真だけでは伝わらない魅力を直感的に伝えることが可能です。これにより、通行人の足を止め、入店を促す強力なアイキャッチとして機能します。
看板の交換はなし!設置場所や時間帯に合わせたコンテンツ配信が可能
デジタルサイネージは、一度設置すれば物理的な「看板の交換」が不要になります。これにより、看板を作り替えるたびにかかっていた制作費や施工費を長期的に削減できます。さらに、デジタルサイネージの多くは「スケジュール配信機能」を備えており、特定の時間帯や曜日に合わせて表示コンテンツを自動で切り替えることが可能です。
例えば、以下のような柔軟な運用が実現できます。
- 飲食店:朝はモーニング、昼はランチ、夜はディナーや宴会メニューを自動で表示。
- 小売店:平日の昼間は主婦層向け、夕方以降や休日はファミリー層向けのコンテンツに切り替え。
- クリニック:診療時間内は診療案内、時間外は休診案内や緊急連絡先を表示。
このように、ターゲットとなる顧客層や状況に応じて最適な情報を配信することで、広告効果を最大化できます。
導入前に確認!デジタルサイネージ看板のデメリットと対策
ここでは、代表的な3つのデメリットと、その具体的な対策について詳しく解説します。導入後の「こんなはずではなかった」を防ぐために、しっかりと確認しておきましょう。
初期費用やランニングコストの負担は?補助金やリース活用でコスト対策を
デジタルサイネージ看板を導入する際、多くの方が最初に懸念されるのが「初期費用」や「ランニングコスト」の問題です。
ディスプレイ本体や設置工事、周辺機器、コンテンツ制作などを含めると、導入時には小規模な屋内設置で20万〜30万円、大型屋外看板では80万〜100万円超が相場になります。また、導入後も電気代や保守費用、システム利用料などのランニングコストも継続的に発生いたします。タンニングコストの相場はシンプルな構成で月3,000円〜、フル運用なら月1〜3万円が目安になっています。
こうした費用負担を軽減する手段として、まず検討いただきたいのが自治体や国の補助金制度です。中小企業向けのIT導入補助金や地域振興関連の補助金など、デジタルサイネージの導入が対象となるケースも多くございます。条件や募集時期があるため、事前に情報収集をされることをおすすめいたします。
また、初期費用を抑える方法としてリース契約やサブスクリプション型のプランも有効です。導入コストを月額に分散できるため、資金繰りにゆとりを持たせながら運用を開始できます。リース契約に関しては契約年数や内容によって大きく費用が異なるため、気になる方は複数のリース会社や機器ベンダーから見積もりを取り、条件や総支払額を比較されることをおすすめいたします。
コンテンツ制作や更新はどうする?テンプレートや外注で運用を効率化
デジタルサイネージの最大の強みは、情報をタイムリーに更新できる点にありますが、これは裏を返せば「常にコンテンツを制作・更新し続けなければならない」ということでもあります。専任の担当者がいない場合、コンテンツ制作が負担となり、次第に情報が古いまま放置されてしまうケースも少なくありません。これでは、高額な投資をした意味がなくなってしまいます。
運用の負担を軽減し、効果を最大化するための対策は以下の通りです。
コンテンツ運用の効率化
- テンプレートが豊富なシステムを選ぶ:専門的な知識がなくても、PowerPointを操作するような感覚でプロ並みのコンテンツを作成できるサービスが増えています。静止画や動画のテンプレートが豊富にあれば、日々の更新作業が格段に楽になります。
- 直感的に操作できるCMSを選ぶ:誰でも簡単にコンテンツの入稿や配信スケジュールを設定できる、分かりやすい管理画面(CMS:コンテンツ管理システム)を備えた製品を選びましょう。スマートフォンやタブレットから遠隔操作できるものであれば、場所を選ばず更新が可能です。
- コンテンツ制作を外注する:自社での対応が難しい場合は、コンテンツ制作を専門の会社や、デジタルサイネージの販売代理店が提供する制作代行サービスに委託するのも一つの手です。クオリティの高いコンテンツを安定的に確保できます。
自社のリソースやスキルレベルに合わせて、「どこまでを自社で行い、どこからを外部に任せるか」を事前に決めておくことが、継続的な運用の鍵となります。
故障や停電などデジタルトラブルのリスクは?バックアップ体制とサポート選び
デジタルサイネージは精密な電子機器であるため、故障や不具合、停電などのデジタルトラブルが発生するリスクを常に抱えています。特に屋外に設置する場合は、雨風や気温差などの影響を受けやすく、屋内に比べて故障の可能性が高まります。
「画面が映らなくなった」「コンテンツが表示されない」といったトラブルが発生すると、訴求効果の低下や業務の停滞にもつながりかねません。そのため、事前の備えが重要です。
安心して運用を続けるためには、次のポイントを確認しましょう。
- 保証とサポート体制を確認する
製品の保証期間や、故障時の対応方法(電話・メール・訪問修理など)を事前に把握しておくことが大切です。特に、すぐに復旧が求められる店舗や施設では、現地対応(オンサイト保守)の有無が重要な選定基準となります。 - 停電復旧機能の有無をチェックする
停電後に自動で電源が入り、設定していたコンテンツが再生される機能があると安心です。復旧作業の手間を省けるうえ、機会損失のリスクも軽減されます。 - 屋外設置には防水・防塵性能が必須
防塵・防水性能を示す「IPコード」を確認し、設置環境に適した機器を選びましょう。これにより、天候による故障リスクを大きく減らすことができます。 - クラウド型CMSの導入でデータを保護する
コンテンツをクラウドで管理しておけば、機器が故障してもデータは保管されたままです。機器交換後も、すぐに元の状態に戻すことが可能です。
このように、機器スペックだけでなく「トラブル時にどんな対応が受けられるか」という視点から、メーカーや販売代理店を選ぶことが、安心・安定した長期運用につながります。
失敗しないデジタルサイネージ看板の選び方!3つのポイントとは
デジタルサイネージ看板の導入効果は、どの製品を選ぶかによって大きく変わります。ここでは、導入を成功させるために欠かせない3つの選び方のポイントを詳しく解説します。
設置場所に合ったタイプを選ぶ!屋外・屋内・スタンド型の特徴をチェック
デジタルサイネージは設置場所によって最適なタイプが異なります。主に「屋外用」「屋内用」「スタンドアロン型」の3種類があり、それぞれの特徴を理解することが重要です。特に屋外用は、防水・防塵性能や直射日光下での視認性が求められます。
| タイプ | 特徴 | 主な設置場所 |
| 屋外用 | 防水・防塵機能が必須。直射日光にも負けない高い輝度(明るさ)を持つ。温度変化への耐性も高い。 | 店舗の軒先、壁面、駐車場、イベント会場など |
| 屋内用 | 天候の影響を受けないため、屋外用に比べて輝度は控えめ。デザイン性が高く、薄型・軽量なモデルが多い。 | 商業施設の通路、店舗内、オフィスのエントランス、駅構内など |
| スタンドアロン型(自立型) | キャスター付きで移動が簡単なモデルが多い。設置工事が不要で、手軽に導入できる。屋内用が主流だが、屋外対応モデルもある。 | 店舗の入口、イベントブース、ショールーム、待合室など |
サイズと明るさの選び方とは?画面の視認性で集客力が変わる
通行人の注意を引き、情報を正確に伝えるためには、ディスプレイの「サイズ」と「明るさ(輝度)」が非常に重要です。設置環境と、誰に・どこから見てほしいのかを具体的にイメージして選びましょう。
画面サイズの選び方
画面サイズは、視聴者との距離によって最適な大きさが変わります。例えば、通行量の多い歩道に向けて遠くからでも認識させたい場合は55インチ以上の大型サイズが、店舗内で商品を手に取る顧客に訴求したい場合は32インチ程度の中型サイズが適しています。設置スペースの広さも考慮して、圧迫感のないサイズを選びましょう。
画面の明るさ(輝度)の選び方
画面の明るさは「カンデラ(cd/㎡)」という単位で表され、数値が大きいほど明るくなります。設置場所の環境光に合わせて選ばないと、画面が暗くて見えなかったり、逆に明るすぎて眩しく感じたりすることがあります。
| 設置環境 | 推奨輝度の目安 |
| 屋内(一般的な照明環境) | 400~700 cd/㎡ |
| 屋内(窓際など外光が入る場所) | 700~1,500 cd/㎡ |
| 屋外(日陰や曇天時) | 1,500~2,500 cd/㎡ |
| 屋外(直射日光が当たる場所) | 2,500 cd/㎡以上 |
コンテンツ更新のしやすさも重要!運用の手間を減らす管理機能とは
デジタルサイネージ看板を長期的に活用する上で、コンテンツの更新作業がどれだけスムーズに行えるかは、非常に重要なポイントとなります。導入当初は業者にすべて任せていたとしても、日々の情報更新やキャンペーン対応などが発生する中で、自社で簡単に運用できる仕組みが整っているかどうかが、運用効率を大きく左右いたします。
特に注目すべきは、CMS(コンテンツ管理システム)の操作性や機能性です。クラウド型CMSであれば、パソコンやスマートフォンから遠隔で複数拠点のサイネージを一括管理でき、急な内容変更にも柔軟に対応可能です。また、曜日や時間帯に応じた自動表示設定や、テンプレートを活用した簡易編集機能が備わっているものを選べば、専門知識がなくても手軽にコンテンツの差し替えが行えます。
反対に、機器ごとにUSBで手動更新が必要なタイプや、操作が複雑なCMSを選んでしまうと、現場での作業負担が大きくなり、更新の手間が業務の妨げになることもございます。
そのため、導入前には実際の操作画面を確認したり、無料トライアルを利用して使用感を確かめておくことをおすすめいたします。運用担当者のスキルや業務体制に合った管理機能を備えた製品を選ぶことが、無理なく継続できる運用体制づくりのカギとなります。
【業種別】デジタルサイネージ看板の活用事例!
ここでは、業種別に具体的なデジタルサイネージの活用事例を紹介します。自社のビジネスにどのように応用できるか、イメージを膨らませてみましょう。
飲食店・小売店の店頭での集客・販促事例
飲食店や小売店では、店頭を通行する人々の足を止め、入店を促すためのツールとしてデジタルサイネージが非常に有効です。紙のポスターとは異なり、動画や音で視覚と聴覚に訴えかけることで、高いアイキャッチ効果が期待できます。
| 活用シーン | 具体的なコンテンツ例 | 期待できる効果 |
| ランチタイムの店頭 | 調理シーンの動画や、シズル感あふれる料理の映像を配信。日替わりメニューを大きく表示。 | 通行人の食欲を刺激し、ランチ客の入店を促進する。 |
| 夕方以降のタイムセール | 「18時〜20時限定!ドリンク半額」など、時間限定のキャンペーン情報をリアルタイムで告知。 | 即時的な購買意欲を喚起し、仕事帰りの顧客などを取り込む。 |
| アパレル店のショーウィンドウ | 新商品のプロモーションビデオや、モデルが商品を着用しているコーディネート例の動画を放映。 | 商品の魅力をダイナミックに伝え、ブランドイメージ向上と入店率アップにつなげる。 |
商業施設・駅での案内・広告配信事例
不特定多数の人が行き交う大規模な商業施設や駅では、情報案内や広告媒体としての役割が大きくなります。大型のディスプレイを設置することで、多くの人々に効率よく情報を届けることが可能です。
| 設置場所 | 活用方法 | メリット・目的 |
| 商業施設の入口・総合案内所 | タッチパネル式のフロアマップ、イベント情報、テナントのセールス情報などを配信。 | 利用者の利便性向上。館内での回遊性を高め、売上向上に貢献する。 |
| 駅のコンコース・ホーム | 列車の運行情報、遅延情報、乗り換え案内、駅周辺の広告などをリアルタイムで表示。 | 利用者に正確な情報を迅速に提供。広告媒体として活用し、新たな収益源を確保する。 |
| エレベーターホール・エスカレーター横 | 各フロアのテナント広告や、季節のイベント案内などを放映。 | 待ち時間や移動時間を活用して情報を刷り込み、効果的なプロモーションを行う。 |
オフィス・工場での情報共有・業務効率化事例
オフィスや工場では、従業員向けの情報共有ツールとしてデジタルサイネージが活躍します。全従業員へ向けてリアルタイムに情報を発信することで、コミュニケーションの活性化や業務効率の改善、安全意識の向上を図ります。
| 目的 | コンテンツ例 | 期待できる効果 |
| 社内情報共有 | 朝礼での共有事項、社内通達、売上目標の進捗グラフ、新入社員の紹介などを表示。 | 情報伝達の漏れを防ぎ、ペーパーレス化を促進。従業員の帰属意識を高める。 |
| 業務の可視化(工場) | 生産ラインの稼働状況、生産目標の達成率、品質管理データをリアルタイムで表示。 | 従業員のモチベーション向上と生産性の改善。問題発生時の迅速な対応を促す。 |
| 安全意識の向上 | 「今週の安全目標」「ヒヤリハット事例」「熱中症対策」などの注意喚起コンテンツを配信。 | 労災事故の防止。従業員の安全に対する意識を常に高く保つ。 |
| 来客対応 | エントランスや受付に来訪者向けのウェルカムメッセージや、会社の紹介動画を表示。 | 企業イメージの向上と、スムーズなおもてなしを実現する。 |
病院・クリニックでの待合室の案内事例
病院やクリニックの待合室では、患者の待ち時間に感じるストレスを軽減し、院内情報をスムーズに伝達する目的で導入が進んでいます。プライバシーに配慮した呼び出しや、有益な情報提供が主な活用方法です。
| 活用シーン | 表示コンテンツ | 患者・病院側のメリット |
| 待合室での順番案内 | 受付番号や診察室番号を表示。「〇〇番の患者様、第2診察室へお入りください」など。 | 【患者】待ち状況が分かり安心できる。【病院】名前で呼び出さないためプライバシーが守れる。 |
| 待ち時間の有効活用 | 健康に関する豆知識、季節性の感染症予防策、新しい治療法の紹介、院内設備の案内などを配信。 | 【患者】有益な情報を得られ、待ち時間の体感が短くなる。【病院】啓蒙活動や自院のPRができる。 |
| 院内情報の告知 | 休診日のお知らせ、担当医の変更案内、予防接種の受付期間などをタイムリーに表示。 | 【患者】重要な情報を逃さず確認できる。【病院】問い合わせ対応の手間を削減し、スタッフの負担を軽減する。 |
デジタルサイネージ看板を設置する際の注意点
デジタルサイネージ看板は、従来の看板と異なり、設置や運用にあたって特有の注意点が存在します。ここでは、デジタルサイネージ導入後の注意点をご紹介します。
屋外設置に関する法令(屋外広告物条例)
屋外にデジタルサイネージ看板を設置する場合「屋外広告物法」および、それに基づいて各地方自治体が定める「屋外広告物条例」を遵守する必要があります。これらの法令は、良好な景観の維持や公衆への危害防止を目的としており、違反した場合は罰則が科される可能性もあるため注意が必要です。
自治体によって規制の詳細は異なりますが、主に以下のような点が定められています。デジタルサイネージは光を発し、映像が動くという特性から、一般的な看板よりも厳しい基準が設けられている場合があります。
| 規制項目の例 | 具体的な内容 |
| 許可申請 | 広告物を表示・設置する際に、自治体への許可申請が必要になります。申請には、設置場所の図面や広告物のデザイン、仕様書などの提出が求められます。 |
| 設置禁止区域・物件 | 景観を保護する地域や、信号機・道路標識の視認性を妨げる場所、街路樹、橋、トンネルなど、広告物の設置が原則として禁止されているエリアや物件があります。 |
| 大きさ・高さの制限 | 設置できる広告物の面積や高さに上限が定められています。地域の景観や建物の規模に応じて基準が異なります。 |
| 輝度(明るさ)の基準 | デジタルサイネージの画面の明るさ(輝度)の上限が定められている場合があります。特に夜間は、周辺環境への配慮や交通の安全確保のため、昼間よりも低い輝度に設定するよう指導されることが一般的です。 |
| 表示内容の制限 | 点滅の速度が速すぎる表示や、赤信号と誤認されるような赤色を多用した表示、運転者の注意を著しく妨げるような映像表現が規制されることがあります。 |
これらの規制は非常に専門的かつ複雑なため、自社だけで判断するのは困難です。デジタルサイネージの設置を検討する際は、必ず事前に設置場所を管轄する自治体の担当部署(都市計画課、まちづくり推進課など)に相談するか、屋外広告物条例に詳しい専門業者に確認しましょう。
放映するコンテンツの著作権や景観条例
デジタルサイネージで放映する映像や音声コンテンツは、自社の魅力や情報を伝える重要な要素ですが、その制作・利用にあたっては権利関係や周辺環境への配慮が不可欠です。
コンテンツの権利関係
自社で制作したオリジナルコンテンツ以外を利用する場合、著作権や肖像権などの権利を侵害しないよう細心の注意が必要です。知らずに権利を侵害してしまうと、損害賠償請求などの大きなトラブルに発展する可能性があります。
| 権利の種類 | 注意すべきポイント |
| 著作権(音楽) | 市販のCDやダウンロードした楽曲などをBGMとして使用する場合、JASRAC(日本音楽著作権協会)などの著作権管理団体への利用許諾申請と使用料の支払いが必要です。商用利用可の著作権フリー音源を利用するのも一つの方法です。 |
| 著作権(映像・画像) | インターネット上で見つけた他人の写真やイラスト、アニメや映画のキャラクターなどを無断で使用することは著作権侵害にあたります。有料または無料のストックフォトサービスを利用する場合も、必ず利用規約を確認し、商用利用や改変が許可されているかを確認しましょう。 |
| 肖像権 | 許可なく特定の個人が識別できる映像や写真を放映すると、肖像権の侵害になる可能性があります。人物を撮影して使用する場合は、必ず本人の許諾を得るか、個人が特定できないようにぼかしなどの加工を施す必要があります。 |
景観条例との調和
屋外広告物条例とは別に、自治体によっては独自の「景観条例」や「景観ガイドライン」を定めている場合があります。特に、歴史的な街並みや自然景観が豊かな地域では、広告物の色彩やデザイン、表示内容が周囲の景観と調和しているかが厳しく問われます。
デジタルサイネージは、その鮮やかな色彩や動きのある映像が周囲から浮いてしまう可能性があります。コンテンツを制作する際は、けばけばしい色使いを避け、地域の雰囲気や街並みに溶け込むようなデザインを心がけることが大切です。こちらも、設置場所の自治体が定める景観に関するルールを事前に確認することが重要です。
まとめ
デジタルサイネージ看板は、静止画中心の従来型看板とは異なり、映像や音声、スケジュール設定機能などを活用して、より戦略的な情報発信が可能になります。成功の鍵は、目的に合った機種選び、無理のない運用体制、そして各種法令や景観への配慮です。
この記事でご紹介した内容を踏まえて、自社にぴったりのデジタルサイネージを導入し、集客力や情報発信力の向上にお役立ていただければ幸いです。
デジタルサイネージの導入をご検討中の方や、デザイン・設置についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問合せください。
あなたの理想に合ったご提案や製作を、専門スタッフが丁寧にサポートします。
![看板製作、ポスター印刷ならP-0 Grand Prix [ピーゼログランプリ]](https://p0gp.com/wp-content/uploads/2020/06/logo-sp-c.png)