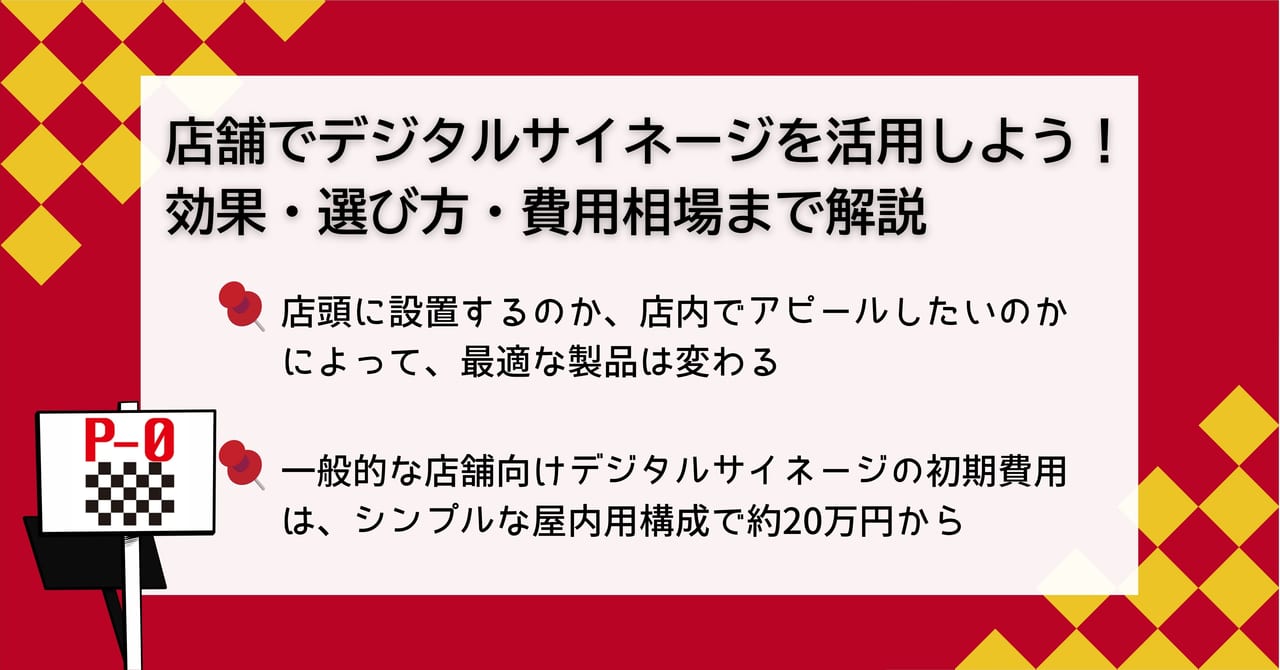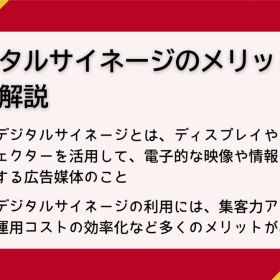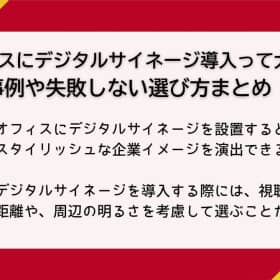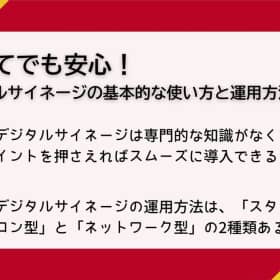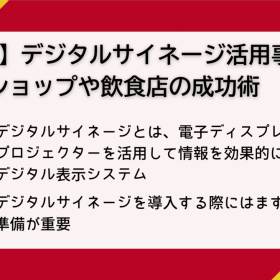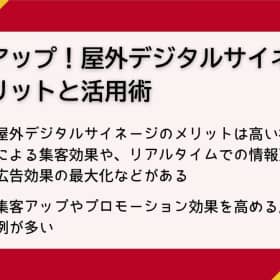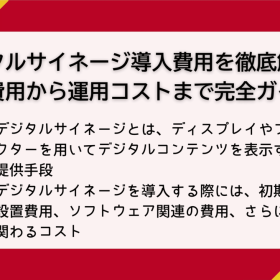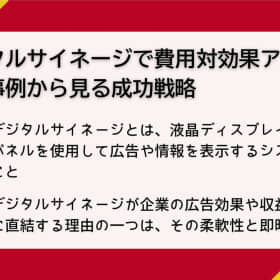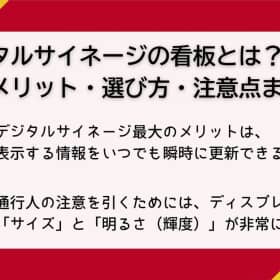デジタルサイネージ
店舗でデジタルサイネージを活用しよう!効果・選び方・費用相場まで解説
店舗の集客や販促に課題を感じている方には、「デジタルサイネージ」の導入がおすすめです。動きのある映像で視線を引きつけ、時間帯や天候に合わせた柔軟な情報発信ができるため、従来の看板以上の効果が期待できます。 本記事では、デジタルサイネージの基本から導入のメリット、選び方のポイント、費用相場、さらには活用できる補助金まで、店舗オーナーの方に役立つ情報をわかりやすく解説します。
目次
デジタルサイネージとは?基本をわかりやすく解説
ここでは、デジタルサイネージの基本的な知識と、従来の看板やポスターとの違いをわかりやすく解説します。
そもそもデジタルサイネージとは?
デジタルサイネージとは、ディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発信するシステムの総称です。「電子看板」や「電子ポスター」とも呼ばれ、駅や空港、商業施設、店舗の軒先など、さまざまな場所で活用されています。
単に映像を流すだけでなく、ネットワークに接続することで、遠隔地から表示する内容をリアルタイムで更新・変更できるのが大きな特徴です。主に以下の要素で構成されています。
- ディスプレイ:情報を表示する液晶ディスプレイやLEDビジョンなど。
- 再生機器(STB):コンテンツのデータを再生するための小型PCや専用端末(セットトップボックス)。ディスプレイに内蔵されているタイプもあります。
- コンテンツ:表示する静止画、動画、テロップなどの情報データ。
- 管理システム(CMS):複数のディスプレイの表示内容やスケジュールを管理するソフトウェア。
これらの仕組みにより、紙媒体では難しかった動的な情報発信を可能にし、人々の視線を集める強力なツールとして普及が進んでいます。
従来の看板やポスターとの違い
デジタルサイネージと従来の看板やポスターとの大きな違いは、「表示できる情報の柔軟性と即時性」にあります。
ポスターや紙の看板は一度制作すると内容の変更が難しく、更新には手間とコストがかかります。それに対してデジタルサイネージは、動画や静止画を含む多彩なコンテンツを表示でき、必要に応じて内容を遠隔ですぐに切り替えることが可能です。
このように、デジタルサイネージは情報の「質」と「鮮度」を飛躍的に向上させることができます。一度設置すれば、印刷コストをかけずに情報を更新し続けられるため、集客効果もふまえ長期的に見るとコストパフォーマンスに優れた新しい媒体といえるでしょう。
店舗にデジタルサイネージを導入する3つの効果とメリット
デジタルサイネージを店舗に導入することで、具体的にどのような効果やメリットが期待できるのでしょうか。ここでは、集客からブランディングまで、店舗運営に役立つ3つの大きなメリットを解説します。
通行客の注目を集めて“足を止める”仕掛けができる
店舗の前を通り過ぎる多くの人々に対して、まず存在に気づいてもらい、興味を持ってもらうことは集客の第一歩です。
デジタルサイネージは、静止画であるポスターや看板とは異なり、動画やアニメーションといった「動き」のあるコンテンツを表示できます。光と動きを伴う映像は、人間の視覚に強く訴えかけるため、通行客の注意を自然に引きつけ、足を止めるきっかけを作り出します。
高い輝度のディスプレイは日中の屋外でも優れた視認性を発揮し、店舗の存在を効果的にアピール。結果として入店率の向上に繋がります。
時間帯や期間限定に合わせた情報発信で販促を強化
デジタルサイネージの大きな強みは、表示するコンテンツをいつでも簡単に、そして即座に変更できる点にあります。これにより、顧客のニーズや状況に合わせたタイムリーな情報発信が可能です。例えば、飲食店であればランチタイムにはランチメニューを、ディナータイムにはコース料理やアルコールメニューを自動で切り替えて表示できます。また、雨が降ってきたら「雨の日限定クーポン」を、夕方には「タイムセール実施中!」といったゲリラ的なキャンペーンも即座に告知でき、販売機会の損失を防ぎます。
ポスターのように印刷して貼り替える手間やコストがかからないため、効率的かつ効果的な販促活動が実現します。
| 業種 | 時間帯・状況 | コンテンツ内容の例 |
| 飲食店 | ランチタイム(11:00-14:00) | 日替わりランチメニュー、お得なセットの紹介 |
| 小売店 | 夕方(16:00-) | タイムセール、お惣菜の割引情報の告知 |
| アパレル | 週末・祝日 | 週末限定のセール情報、新着アイテムの紹介 |
| 全般 | 雨天時 | 雨の日限定ポイントアップ、割引クーポンの発行 |
店舗の雰囲気づくり・ブランドイメージの向上にも貢献
デジタルサイネージは、単なる情報伝達ツールにとどまりません。空間を彩るインテリアの一部として、店舗の雰囲気づくりやブランドイメージの向上にも大きく貢献します。
例えば、アパレルショップではブランドの世界観を表現したスタイリッシュな映像を、美容室やクリニックではリラックスできる環境映像や清潔感を伝える映像を流すことで、空間全体の質を高めることができます。
洗練された映像コンテンツは、顧客に「おしゃれ」「先進的」「信頼できる」といったポジティブな印象を与え、顧客体験(CX)の向上にも繋がります。最先端のデジタル機器を導入していること自体が、企業の先進性や差別化のアピールにもなるのです。
失敗しない!店舗用デジタルサイネージの選び方と5つのポイント
デジタルサイネージは、自店舗の目的や環境に合わない製品を選んでしまうと失敗につながりかねません。ここでは、店舗用デジタルサイネージ選びで失敗しないための5つの重要なポイントを解説します。
① 屋内用と屋外用の違いは?設置場所と目的を明確にする
デジタルサイネージを選ぶ最初のステップは、「どこに設置して、誰に、何を伝えたいのか」を明確にすることです。設置場所が屋内か屋外かによって、求められる性能が大きく異なります。
屋内用と屋外用では、特に「防水・防塵性能」と「耐久性」に大きな違いがあります。屋外に屋内用のディスプレイを設置すると、雨や塵によってすぐに故障してしまうため、必ず設置場所に適したモデルを選びましょう。
例えば、店頭に設置して通行人の入店を促したいのか、店内の商品棚で特定の商品をアピールしたいのかによって、最適な製品は変わります。まずは設置場所と目的を明確にすることが、失敗しないサイネージ選びの第一歩です。
② ディスプレイのサイズと輝度で選ぶ
設置場所と目的が決まったら、次は具体的なディスプレイのスペックを選んでいきます。特に重要なのが「サイズ」と「輝度(きど)」です。
ディスプレイのサイズ
ディスプレイのサイズは、設置場所の広さや、視聴者との距離(視認距離)を考慮して選びます。大きすぎると圧迫感を与え、小さすぎると訴求力が弱まります。一般的に、店舗でよく利用されるのは43~65インチ程度のサイズですが、設置環境に合わせて最適なものを選びましょう。
- 近距離で見る場合(商品棚など):32インチ以下
- 店舗入口や通路など:43~55インチ
- 広い空間や遠くから見せる場合:65インチ以上
ディスプレイの輝度
輝度とはディスプレイの明るさを示す指標で、「cd/㎡(カンデラ毎平方メートル)」という単位で表されます。この数値が高いほど、明るい場所でも視認性が高くなります。特に屋外や日差しの入る窓際では、輝度が低いと画面が暗くて見えづらくなり、サイネージの効果が半減してしまいます。
| 設置環境 | 推奨される輝度の目安 | 具体例 |
| 店内(照明の落ち着いた場所) | 350~500 cd/㎡ | 一般的なテレビと同程度の明るさ。店内の壁面など。 |
| 屋内(窓際など外光が入る場所) | 700~1,500 cd/㎡ | 外の明るさに負けない視認性を確保。路面店の窓際など。 |
| 屋外(日陰・曇天時) | 1,500~2,500 cd/㎡ | 日中でもコンテンツをはっきりと表示。ビルの軒下など。 |
| 屋外(直射日光が当たる場所) | 2,500 cd/㎡以上 | 強い日差しの下でも高い視認性を維持。日光を遮るものがない場所。 |
③ 目的に合ったコンテンツの作成と運用方法を考える
デジタルサイネージは、ディスプレイという「器」だけあっても機能しません。その中で放映する「コンテンツ」と、それを管理・配信する「運用方法」が効果を左右します。
コンテンツの作成方法
魅力的なコンテンツを継続的に発信することが重要です。作成方法は、自社で内製するか、制作会社に外注するかの2択が基本です。最近では、専門知識がなくてもパワーポイントのような操作でコンテンツを作成できる、テンプレートが豊富なCMS(コンテンツ管理システム)も増えています。
コンテンツの運用方法
コンテンツの更新・配信方法には、主に「スタンドアロン型」と「ネットワーク型」の2種類があります。
| 運用方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
| スタンドアロン型 | USBメモリやSDカードをディスプレイに直接挿してコンテンツを再生する。 | ・導入コストが安い
・ネット環境が不要 |
・更新のたびに現地作業が必要
・複数台の管理が大変 ・リアルタイムな情報発信ができない |
| ネットワーク型 | インターネット経由で、PCやスマホから遠隔でコンテンツを更新・管理する。(CMSを利用) | ・遠隔で一括更新が可能
・複数台の管理が容易 ・時間帯別の配信設定(スケジューリング)ができる |
・月額のシステム利用料がかかる
・ネット環境が必須 |
更新頻度が低い場合はスタンドアロン型、複数店舗で運用する場合やタイムセールなど頻繁な情報更新を行いたい場合はネットワーク型がおすすめです。
④ 導入形態(購入・レンタル・リース)で選ぶ
デジタルサイネージの導入形態には、大きく分けて「購入」「レンタル」「リース」の3つの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、予算や運用計画に合わせて最適な方法を選びましょう。
| 導入形態 | 特徴 | 向いているケース |
| 購入 | 一括または分割で支払い、自社の資産として所有する。ランニングコストは電気代やメンテナンス費のみ。 | ・長期的に利用する予定がある
・自社の資産として保有したい ・初期投資の予算を確保できる |
| レンタル | 必要な期間だけ月額料金で機材を借りる。契約期間の縛りが短く、短期利用も可能。 | ・イベントなど短期間だけ利用したい
・導入効果を試してみたい ・初期費用を抑えたい |
| リース | リース会社が購入した機材を、3年~6年程度の長期間、月額料金で借りる。契約満了後は再リースや返却を選ぶ。 | ・初期費用を抑えて長期間利用したい
・最新機種への入れ替えを検討している ・費用を経費として処理したい |
初期費用を抑えたい場合はレンタルやリース、長期的なコストを抑えたい場合は購入が適しています。まずはレンタルでお試し導入し、効果を実感してから購入に切り替えるといった方法も有効です。
⑤ サポート体制を確認する
デジタルサイネージは精密機器のため、万が一の故障やトラブルは避けられません。「画面が映らなくなった」「コンテンツの更新方法がわからない」といった際に、迅速に対応してくれるサポート体制があるかは非常に重要です。
導入を検討しているベンダーや代理店に、以下の点を確認しておくと安心です。
- 導入時のサポート:設置や初期設定まで行ってくれるか。
- 操作方法のサポート:電話やメールでの問い合わせ窓口はあるか。受付時間はいつか。
- 故障時の対応:保証期間はどのくらいか。修理は現地で行う「オンサイト保守」か、機器を送付する「センドバック保守」か。代替機の貸し出しはあるか。
- コンテンツ制作のサポート:コンテンツ作成の代行や相談に応じてくれるか。
特に、デジタル機器の操作に不安がある場合は、導入から運用、万が一のトラブルまで一貫してサポートしてくれるベンダーを選ぶことを強くおすすめします。
店舗向けデジタルサイネージの費用相場は?内訳も紹介
店舗にデジタルサイネージを導入する際、最も気になるのが「費用」ではないでしょうか。
費用は大きく分けて、導入時に一度だけかかる「初期費用」と、運用を続けるために継続的に発生する「ランニングコスト」の2種類があります。ここでは、それぞれの費用の内訳と相場を詳しく解説します。
導入時にかかる初期費用はいくらが相場?
初期費用は、デジタルサイネージを「購入」する場合に発生する費用です。ディスプレイ本体だけでなく、ソフトウェアや設置工事にも費用がかかります。
一般的な店舗向けデジタルサイネージの初期費用は、シンプルな屋内用構成で約20万円から、高機能なシステムでは100万円を超えるケースもあります。レンタルやリースを利用する場合は、これらの初期費用が月額料金に含まれるため、導入時の負担を大幅に軽減できます。
一般的な内訳と費用相場は以下の通りです。
| 費用項目 | 内容 | 費用相場 |
| ハードウェア費 | ディスプレイ本体、STB(セットトップボックス)、スタンドや壁掛け金具など、機器一式の購入費用です。 | 約10万円~100万円以上 |
| ソフトウェア費 | コンテンツの配信スケジュールなどを管理するCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)のライセンス購入費用です。買い切り型の場合に発生します。 | 約5万円~30万円 |
| コンテンツ制作費 | ディスプレイに表示する静止画や動画コンテンツの制作を専門業者に依頼する場合の費用です。自作する場合はかかりません。 | 静止画:1枚数千円~
動画:1本数万円~ |
| 設置工事費 | ディスプレイの壁掛け・天吊り設置や、それに伴う配線工事などが必要な場合の費用です。スタンド型でコンセントに挿すだけの場合は不要です。 | 約5万円~20万円 |
運用にかかるランニングコストの費用相場は?
ランニングコストは、デジタルサイネージの運用を継続するために必要な月々の費用です。主に、ソフトウェア利用料や電気代、コンテンツの更新費用などが挙げられます。
ランニングコストは、運用方法によって大きく変動します。例えば、コンテンツを自社で制作・更新すれば外注費はかかりません。費用を抑えたい場合は、どこを自社で行い、どこを外部に委託するのかを事前に計画することが重要です。
| 費用項目 | 費用相場(月額) | 内容 |
| ソフトウェア利用料 | 約3,000円~2万円 | CMSをサブスクリプション(月額課金)で利用する場合の費用です。レンタルやリースプランに含まれていることも多いです。 |
| コンテンツ更新費 | 都度見積もり | 季節のキャンペーンや新商品の案内に合わせて、定期的にコンテンツの制作・更新を外部に依頼する場合の費用です。 |
| 電気代 | 約2,000円~1万円 | ディスプレイの消費電力に応じた電気料金です。サイズや輝度、稼働時間によって変動します。 |
| 保守・サポート費用 | 約3,000円~1万円 | 機器の故障時に対応してもらうための保守契約料です。プランによってサポート範囲が異なります。 |
| 通信費 | 約3,000円~5,000円 | ネットワーク経由でコンテンツを配信する場合のインターネット回線費用です。既存の店舗回線を利用する場合は追加費用はかかりません。 |
知らないと損!デジタルサイネージに使えるおすすめの補助金
デジタルサイネージの導入は設備投資にあたるため、国や地方自治体が提供する補助金や助成金の対象となる場合があります。費用負担を軽減するために、活用できる制度がないか確認してみましょう。
代表的な補助金には、以下のようなものがあります。
- IT導入補助金:中小企業や小規模事業者が業務効率化や売上アップのためにITツール(CMSなど)を導入する際に、その経費の一部を補助する制度です。
- 小規模事業者持続化補助金:小規模事業者が販路開拓や生産性向上のために行う取り組みを支援する制度で、デジタルサイネージを広告宣伝費として活用する場合に対象となる可能性があります。
- 事業再構築補助金:思い切った事業の再構築に取り組む事業者を支援する制度で、新たな事業の一環としてデジタルサイネージを導入する場合に活用できるケースがあります。
- 各地方自治体の補助金:都道府県や市区町村が独自に設けている補助金・助成金制度です。DX推進や商店街活性化などを目的としたものが多く、お住まいの地域の情報を確認することをおすすめします。
これらの補助金は、公募期間や申請要件が定められており、毎年内容が変更される可能性があります。申請を検討する際は、必ず各制度の公式サイトで最新の情報を確認してください。補助金を活用することで、導入コストを大幅に抑えられる可能性があるため、積極的に情報を収集しましょう。
Q&A|デジタルサイネージの店舗導入でよくある質問
ここでは、店舗オーナー様がデジタルサイネージの導入を検討する際によく抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。
Q. コンテンツは自分で作れますか?
- はい、専門的な知識がなくてもご自身で作成可能です。コンテンツの作成方法には、主に以下の4つの方法があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身のスキルや目的に合った方法を選びましょう。
| 作成方法 | 特徴 | こんな方におすすめ |
| PowerPoint/Keynoteなど | 普段から使い慣れたプレゼンテーションソフトで作成できます。静止画や簡単なテキストアニメーションの作成に向いています。 | パソコン操作に慣れており、まずはコストを抑えて手軽に始めたい方。 |
| Canvaなどのデザインツール | 無料または安価で利用できるデザインツールです。おしゃれなテンプレートが豊富で、直感的な操作でプロ並みのデザインが可能です。 | デザイン性にこだわりたいが、専門的なデザインソフトは使えない方。 |
| CMS(コンテンツ管理システム) | デジタルサイネージ専用のシステムです。テンプレート利用はもちろん、遠隔からの更新や複数台の一括管理、スケジュール配信など高度な機能が利用できます。 | 複数店舗で運用したい方、時間帯に合わせてタイムリーな情報発信をしたい方。 |
| 制作会社に外注 | プロのデザイナーや映像クリエイターに依頼する方法です。店舗のブランドイメージに合った、訴求力の高い高品質なコンテンツを制作してもらえます。 | 高品質な映像コンテンツを求めている方、コンテンツ制作に時間をかけられない方。 |
作成したコンテンツは、USBメモリをディスプレイに挿して再生する方法や、ネットワーク経由で配信する方法など、機種によって再生方法が異なります。
Q. コンセントのない場所にも設置できますか?
- はい、バッテリー搭載型のデジタルサイネージであれば、電源(コンセント)がない場所にも設置できます。
バッテリー搭載型は、店舗の入口や催事スペースなど、配線が難しい場所や人の往来が多い場所での活用に非常に便利です。配線が不要なため、見た目がすっきりとし、つまずきなどの事故防止にも繋がります。ただし、連続再生できる駆動時間には限りがあるため注意が必要です。一般的には5時間から10時間程度のモデルが多いですが、利用したい時間に合わせて製品仕様を必ず確認しましょう。また、バッテリーを内蔵している分、通常のスタンドアロン型よりも重量が増す傾向にあります。
Q. 屋外に設置したら盗難やいたずらが心配ですが、対策はありますか?
- はい、屋外設置を想定したモデルには、盗難やいたずら、故障を防ぐための様々な対策が施されています。
屋外用デジタルサイネージを選ぶ際は、以下のポイントを確認してください。
- 盗難対策:本体を地面にアンカーボルトで固定できるタイプや、機器収納部の扉にシリンダーキーが付いている筐体(きょうたい)を選ぶと安心です。セキュリティワイヤーを取り付けることも有効な対策となります。
- いたずら・破損対策:ディスプレイの表面が強化ガラスで保護されているモデルを選びましょう。硬い物で叩かれたり、衝撃が加わったりしても破損しにくくなっています。
- 防水・防塵性能:屋外では雨や砂埃が故障の原因となります。「IPコード」と呼ばれる防水・防塵の保護等級を確認し、設置環境に適したものを選びましょう。一般的に屋外では「IP55」以上が推奨されます。
これらの対策が施された堅牢なモデルを選ぶことに加え、万が一の盗難や破損に備えて、動産総合保険に加入することも有効な選択肢の一つです。
まとめ
デジタルサイネージは、店舗の集客力を高めるだけでなく、ブランドのイメージアップや効率的な販促にもつながる強力なツールです。成功させるためには、設置場所や目的に合った機種を選ぶことに加え、運用体制やコンテンツの工夫も欠かせません。補助金制度の活用も視野に入れつつ、この記事を参考に、あなたの店舗の魅力をより多くの人に届けられる最適な一台を導入してみてください。
デジタルサイネージの導入をご検討中の方や、デザイン・設置についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問合せください。
あなたの理想に合ったご提案や製作を、専門スタッフが丁寧にサポートします。
![看板製作、ポスター印刷ならP-0 Grand Prix [ピーゼログランプリ]](https://p0gp.com/wp-content/uploads/2020/06/logo-sp-c.png)